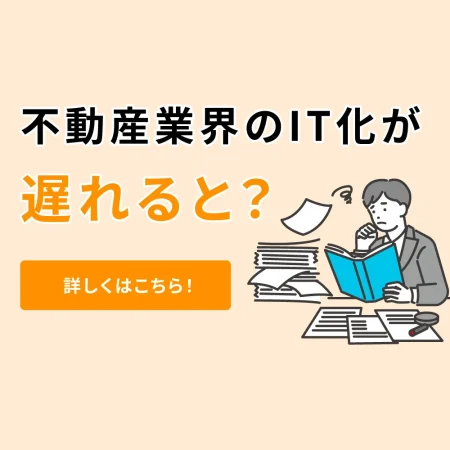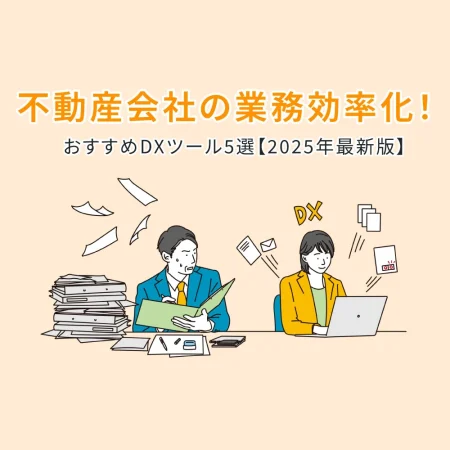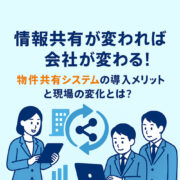不動産業務を効率化!物件共有システムのおすすめと選び方【中小企業向け】

不動産業界では、いまだにFAXやエクセルなどのアナログな方法で物件情報を管理・共有しているケースが少なくありません。営業担当が紙の図面を持ち歩き、電話やメールでやり取りを繰り返す…。そんな光景は、多くの不動産会社で「当たり前」のように存在してきました。
しかしこのようなやり方では、情報の伝達ミスや重複登録、対応の遅れによる機会損失など、業務効率の低下を引き起こす可能性があります。特に複数人・複数拠点で動く組織では、リアルタイムでの情報共有ができないことが、大きなハンデとなります。
こうした課題に対処する手段として、いま注目されているのが「物件共有システム」の導入です。
デジタルツールを活用することで、物件情報を瞬時にチーム全体で共有し、社内外の連携を強化する仕組みが構築できます。さらに近年では、地図や成約履歴との連携、SNSへの自動投稿機能など、便利な機能を備えたサービスも登場しており、中小規模の不動産会社でも手軽に導入できる選択肢が増えています。
本記事では、そうした「物件共有システム」の概要から導入メリット、選び方のポイント、さらにおすすめのツールまでを解説します。
物件共有システムとは?
物件共有システムとは、不動産会社内やグループ会社、取引先企業などの間で物件情報をリアルタイムに共有し、業務の効率化を図るためのITツールです。これまで紙やエクセルで個別に管理されていた情報を一元化し、スムーズな情報伝達と活用を可能にします。
多くのシステムでは、物件の基本情報だけでなく、図面・画像・地図情報・成約ステータス・価格履歴なども紐づけて共有することができ、営業活動や経営判断にも役立ちます。
★関連記事:物件管理システムとは?不動産業界での活用事例を徹底解説!
定義と役割(社内・他社・顧客との情報共有)
物件共有システムの最も大きな役割は、社内外の関係者が同じ情報を同じタイミングで確認できる環境をつくることです。
社内では、営業担当・仕入担当・事務スタッフが一つのシステム上で情報を確認・更新し、業務の抜け漏れや二重対応を防止します。社外では、他の不動産会社や協力企業とも情報を共有し、マッチング精度や成約スピードを向上させることが可能になります。
さらに、顧客との接点でも有効です。例えば、接客中にタブレットで物件一覧を見せたり、地図上で周辺情報と合わせて提案したりすることで、顧客満足度の高い提案ができるようになります。
使われる場面(物件の登録・マッチング・顧客管理・社内教育など)
物件共有システムは、単なる「情報管理ツール」ではなく、営業・業務・教育といった多様なシーンで活用されています。
- 物件登録と更新:仕入れた物件をすぐに登録し、社内やグループ内に通知。最新情報の共有がスムーズに。
- マッチング業務:顧客の希望条件に合致する物件を瞬時に検索・提案可能。見逃しや対応遅れを防ぎます。
- 顧客管理(CRM)との連携:過去のやりとりや紹介履歴を一元管理し、顧客対応の質を向上。
- 社内教育・ナレッジ共有:成約事例や販売戦略を蓄積し、新人教育や社内勉強会で活用。
このように、物件共有システムは日々の業務の土台となるツールとして、多くの場面で力を発揮します。
従来の手法と比べたメリット(スピード・精度・情報の一元化)
従来は、物件情報を紙・FAX・エクセル・口頭連絡などで個別に管理・共有していましたが、これらは手間がかかるうえにヒューマンエラーが起きやすいという課題がありました。
物件共有システムを導入することで、以下のようなメリットが得られます。
- スピード:情報更新と共有がリアルタイムで反映され、対応が迅速に。紹介のタイミングを逃しません。
- 精度:情報の重複や更新漏れを防ぎ、常に最新で正確な情報を確認可能。
- 一元化:物件、顧客、成約情報などが一つのプラットフォームにまとまり、チーム内の連携がスムーズに。
とくに複数人で営業活動を行うチームや、他社との連携が多い会社にとっては、導入効果の大きい仕組みです。
物件共有システムを導入するメリット
物件共有システムは、単に「便利なツール」というだけでなく、業務の質やスピード、成約率に直結する本質的な効果をもたらします。ここでは、導入によって得られる代表的なメリットを4つの観点からご紹介します。
情報伝達のスピードアップ
物件の新着情報や価格変更、成約状況など、変化の早い情報を即座に関係者へ共有できるのが、物件共有システムの大きな強みです。
従来はFAXや電話、メールで逐一連絡する必要があり、情報伝達にタイムラグが生じていました。これが原因で、「知らないうちに成約済になっていた」「紹介したかった物件が消えていた」などの機会損失が頻発していました。
物件共有システムを活用すれば、リアルタイムで情報が更新・通知されるため、社内だけでなく他社との連携スピードも格段に向上。紹介のタイミングを逃すことがなくなります。
営業効率の向上(内見調整、マッチング精度)
物件共有システムは、営業活動の効率化にも直結します。特に以下の2つの業務において、大きな効果が期待できます。
- 内見の調整:空室状況や鍵の管理、現地地図、備考情報などを一元管理できるため、担当者同士の連携がスムーズに。
- マッチング業務:顧客の希望条件に応じて、最適な物件を瞬時に検索・提示可能。対応スピードが上がり、成約率も向上します。
また、写真や地図、周辺情報などもシステム内で確認できるため、提案の質も高まり、顧客満足度にも貢献します。
データの蓄積による相場感の把握と教育活用
物件共有システムには、過去の成約情報や価格推移、反響履歴などが蓄積されていきます。これにより、以下のような活用が可能になります。
- 相場感の把握:エリア別・種別別に成約価格の傾向を把握できるため、仕入・販売価格の妥当性を判断しやすくなる。
- 新人教育への活用:過去の成功事例や提案履歴を教材として活用でき、経験の浅いスタッフでも早期に実力をつけやすい。
属人化しがちな「経験と勘」に依存せず、会社全体でナレッジを共有・活用できる環境が整うことは、大きな競争力となります。
他社連携による成約率アップ
物件共有システムの中には、他社とも物件情報を共有できる仕組みを持つものがあります。これにより、自社の在庫だけでなく、提携先の情報も活用したマッチング提案が可能になります。
たとえば、A社が仕入れた物件をB社が抱える顧客へ紹介し、両社の協力によって成約に至るといったケースも多くあります。
また、共有範囲を自由に設定できるシステムであれば、信頼できる企業間で限定的に情報を開放し、余計な競合リスクを回避しつつ連携できます。
このように、物件共有システムは会社の枠を超えた協力体制の構築にも役立ち、売上機会の最大化につながるのです。
★関連記事:収益性を向上させる非公開物件管理システム導入のメリットと具体的手順
物件共有システムの選び方(比較ポイント)
物件共有システムと一口にいっても、機能や料金体系、使い勝手はサービスごとに大きく異なります。導入を成功させるためには、自社の業務スタイルやスタッフのITリテラシーに合ったツールを選ぶことが重要です。
ここでは、導入時にチェックすべき5つの比較ポイントをご紹介します。
地図連携・成約履歴の可視化
近年の物件共有システムでは、Googleマップなどの地図サービスと連携して、物件情報を視覚的に管理できるものが増えています。
地図上に物件を表示できると、エリア内での分布や競合状況が一目で把握でき、営業エリアの戦略立案や仕入判断にも活用可能です。また、過去の成約履歴や価格変動を地図と連動して表示できる機能があると、相場感の把握や顧客への説明にも説得力が生まれます。
視覚的なツールは、営業資料としての活用や新人教育にも役立つため、「地図ベースで情報を見られるか」は重要な比較ポイントとなります。
他社との物件情報共有機能
他社との連携機能があるシステムでは、自社の仕入れた物件を他社にも共有・公開できたり、他社が保有する物件情報を自社でも検索・提案できるようになります。
特に、同じエリアに拠点を持つ不動産会社との連携がしやすい仕様であれば、“持ちつ持たれつ”の関係構築によって成約のチャンスが広がるでしょう。
一方で、情報公開の範囲や制限を柔軟に設定できるかも重要です。無制限に公開されると、情報漏洩や競合リスクにもつながるため、共有範囲をコントロールできるシステムを選ぶのが理想的です。
SNSや自社HPとの連携
集客力を強化したい企業には、SNS(InstagramやXなど)や自社ホームページと連動できるシステムがおすすめです。
物件情報をシステム上に登録すれば、そのまま自動でSNS投稿・ポータル反映・Web公開ができる機能があると、マーケティング活動にかかる時間と労力を大幅に削減できます。
物件ごとのランディングページを自動生成できるツールもあり、「物件掲載から問い合わせ獲得まで」の導線が整っているかは、選定時に注目したいポイントです。
導入のしやすさ(UI、サポート体制)
どれほど多機能でも、使いこなせなければ意味がありません。特に中小不動産会社やITに不慣れなスタッフが多い企業では、操作が直感的であること(UIのわかりやすさ)は非常に重要です。
また、導入時の初期設定やデータ移行、操作説明などを丁寧にサポートしてくれるベンダーであれば、導入ハードルが大きく下がります。
「誰が使っても迷わないか?」「導入後のフォロー体制は十分か?」といった観点で比較すると、ミスマッチを防ぎやすくなります。
費用対効果(料金と機能のバランス)
物件共有システムには、月額課金型、従量課金型、買い切り型などさまざまな料金体系があります。安価なプランでも必要な機能が揃っていればコストパフォーマンスは高く、逆に高機能すぎて使いこなせないツールは“宝の持ち腐れ”になりがちです。
特に中小企業の場合、「最低限の機能でスタートでき、必要に応じて拡張できる柔軟性」があるかを確認することが大切です。
システムの導入費や月額費用だけでなく、業務効率の改善度・売上へのインパクトを含めた総合的な費用対効果で比較する視点を持ちましょう。
中小不動産会社におすすめの物件共有システム
中小規模の不動産会社にとって、物件共有システムの導入は「業務効率化」と「成約機会の最大化」を実現するうえで非常に有効な手段です。ただし、大手向けの高機能・高価格なシステムではオーバースペックとなり、かえって運用の負担になることもあります。
ここでは、中小企業目線で「扱いやすく、効果を実感しやすい」物件共有システムの特徴を比較しながらご紹介します。
各社の特徴を簡単に比較
現在提供されている物件共有システムには、それぞれ以下のような特徴があります。
| 特徴 | 解説 |
|---|---|
| 地図連携型 | Googleマップなどと連携し、物件の所在地を視覚的に把握可能。エリアの重なりや競合状況も一目でわかる。 |
| 外部共有に強いタイプ | 他社不動産会社との情報共有がしやすい。紹介協力が前提の業務スタイルに適している。 |
| SNS・Web連携型 | Instagramや自社サイトと連動し、登録した物件を自動で公開・発信できる。マーケティング効果も狙える。 |
| CRM・顧客管理一体型 | 顧客情報・希望条件と物件を紐づけて管理でき、マッチング精度が高まる。 |
| シンプル機能重視型 | あえて機能を絞り、エントリーユーザーでも使いやすい設計。低コスト・簡単導入が可能。 |
どのタイプを選ぶべきかは、「自社の業務フロー」や「物件の流通スタイル」に合っているかどうかがポイントになります。
「ITが苦手でも使える」「導入しやすい」などの視点で評価
中小の不動産会社にとって、物件共有システム選びで特に重視すべきなのは以下のようなポイントです。
操作が簡単でわかりやすい
システムの操作画面が直感的で、「新人でもすぐに使える」「マニュアルを読まなくても扱える」レベルのUI設計がされているかは重要です。とくに、Excel感覚で入力・検索できる設計であれば、現場への定着も早くなります。
初期費用が抑えられる
大規模なカスタマイズや専用開発が不要で、月額課金だけで始められるシステムは、導入のハードルが低く、安心してスタートできます。導入前に無料トライアルやデモが用意されているかも確認したいところです。
サポート体制がしっかりしている
「ITは苦手だけど、効率化したい」と考える企業にとって、導入時の支援や運用サポートの手厚さは非常に大きな安心材料となります。電話・メール・チャットなど、問い合わせ対応が複数あると理想的です。
成果につながる仕組みがある
「業務効率化」だけでなく、「反響獲得」や「成約率アップ」など、成果に直結する機能を持っているかも判断基準です。SNSとの連携や、地図+成約履歴表示などが代表的な要素です。
情報共有とDXを両立したい方へ:「PPZE(ププゼ)」のご紹介
ここまで、物件共有システムのメリットや選び方について詳しく解説してきました。
最後に、中小不動産会社の業務効率化とDX推進の両立を実現できるツールとして注目されている、物件共有システム「PPZE(ププゼ)」をご紹介します。
PPZEとは?(物件を地図上で俯瞰・成約情報の可視化・簡単操作)
「PPZE(ププゼ)」は、不動産業務の現場で生まれた課題をもとに開発された、中小不動産会社のための物件共有・管理システムです。
最大の特徴は、地図上に物件を可視化できるインターフェース。Googleマップと連携し、物件の所在地や成約履歴を俯瞰して確認できるため、エリアごとの市場状況を直感的に把握できます。
また、成約済み物件や価格履歴を参照することで、仕入判断や価格設定の参考資料としても活用可能。情報共有だけでなく、経営・営業判断の支援にもつながる設計となっています。
中小不動産業者でも簡単に導入できるシンプルなUI
PPZEのもう一つの大きな魅力は、「誰でも使いこなせる」シンプルで直感的なUI設計です。
ITに不慣れなスタッフでも、感覚的に操作できるため、導入初日から現場での実践が可能。複雑な操作は不要で、物件の登録・検索・公開がスムーズに行えます。
また、余計な機能をそぎ落とした設計により、導入コストや学習負担も最小限に抑えられている点が、中小規模の事業者から高く評価されています。
Googleマップ連携/物件投稿・SNS連携/教育活用にも最適
PPZEは、Googleマップとの連携による地図表示機能だけでなく、以下のような実務に役立つ機能も充実しています。
- 物件投稿機能:社内外に向けた物件情報の共有が簡単に。掲載設定の公開範囲も柔軟に調整可能です。
- 資料作成機能:物件一覧に投稿した情報を元に、販売図面、物件概要書の作成がボタン一つで可能です。
- 社内教育・成約事例の蓄積:過去の販売実績やコメントを蓄積でき、新人育成や営業戦略の共有にも活用可能です。
情報共有を超えて、集客・教育・戦略設計までをサポートする「不動産業務の土台」として、PPZEは多くの現場で導入が進んでいます。
【導入実績】【活用例】【料金概要(リンクへ誘導)】
- 導入実績:すでに複数の中小不動産会社がPPZEを導入し、社内の情報共有スピードが格段に向上したとの声が多数出ています。
- 活用例:
- 販売部門と仕入部門の連携強化
- 成約価格をもとにした価格査定精度の向上
- SNS連携による自社ブランドの認知拡大 - 料金概要:導入費無料・月額定額制で、必要最低限からスタート可能。詳細は公式サイトをご覧ください。
→ PPZE公式サイトはこちら
情報共有と業務効率化を両立する、最適な一歩とは?
不動産業界では今後、「スピーディーな情報共有」と「DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務効率化」の重要性がますます高まっていくと予想されます。
FAXやエクセルによるアナログなやり取りから脱却し、リアルタイムで正確な情報を共有することで、顧客対応の質やスピードが大きく向上します。さらに、データの蓄積や活用により、営業戦略の高度化や社員教育の強化にもつながります。
そのためには、「自社の規模や業務フローに合った物件共有システムを選ぶこと」が何よりも重要です。機能が豊富すぎて使いづらいツールを選んでしまうと、逆に現場が混乱してしまうこともあります。
特に中小規模の不動産会社にとっては、
- 操作が簡単で現場に定着しやすい
- 導入・運用コストが明確
- 現実的に成果につながる機能がそろっている
といった条件を満たすシステムが理想的です。
そこでおすすめしたいのが、物件管理・共有・成約分析をオールインワンで実現する「PPZE(ププゼ)」です。
まずは、あなたの会社で「どんな情報共有・DXができるか」公式サイトでチェックしてみてください。
→ PPZE公式サイトはこちら
まずは、14日間の無料トライアルから始めてみませんか?