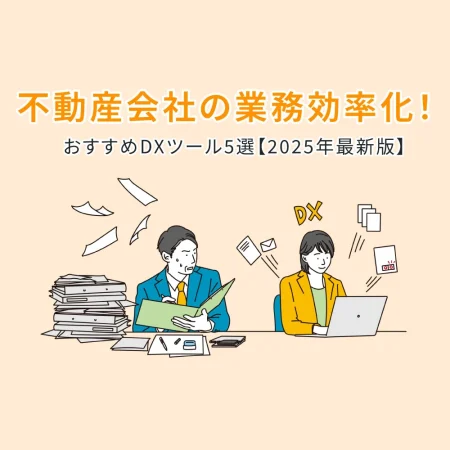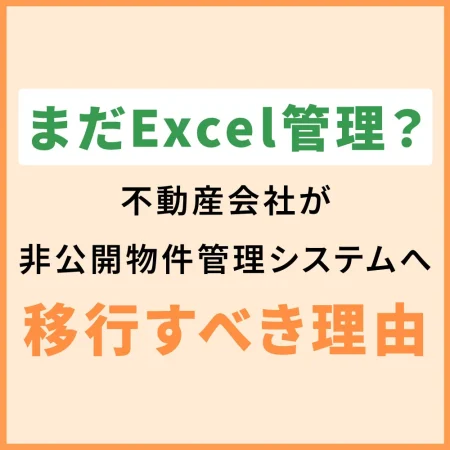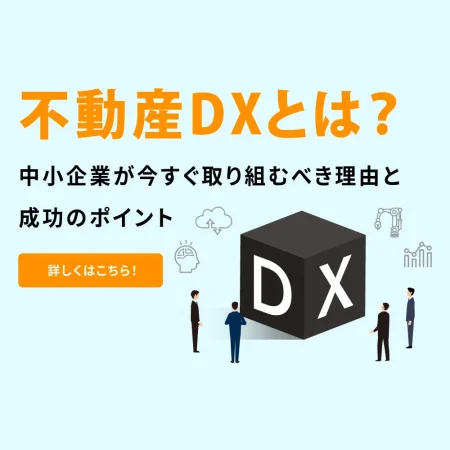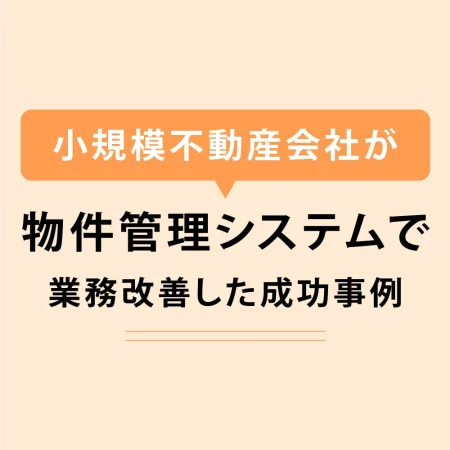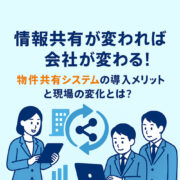後悔しないための「不動産・物件共有システム」の選び方を現場目線で徹底解説
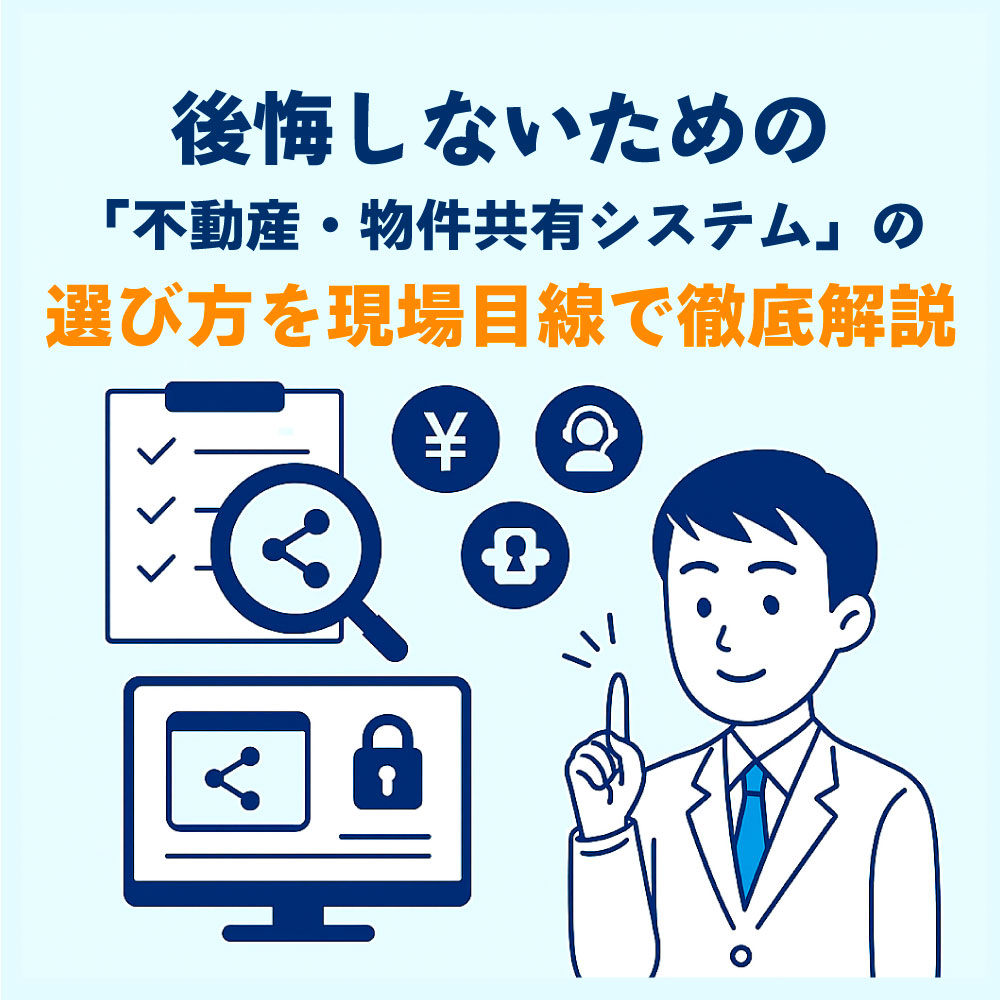
不動産業界でもデジタル化(DX)の波が加速する中、業務効率を左右するのが「物件情報の共有体制」です。
いまだにFAXやエクセルを使って物件を管理している企業も多く、情報の伝達ミスや重複、共有の遅れが商機を逃す原因となっています。特に複数人で動く営業現場では、正確でスピーディーな情報共有こそが成約率を大きく左右する要素です。
本記事では、そんな不動産会社にとって欠かせない「物件共有システム」の選び方のポイントと注意点をわかりやすく解説。さらに、中小不動産会社にも適したシステム「PPZE(ププゼ)」の特徴もご紹介します。導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
物件共有システムとは?
物件共有システムとは、不動産会社が取り扱う物件情報を一元的に管理し、社内外の関係者と効率よく共有するためのツールです。紙の図面やエクセルファイルといったアナログ管理では限界がある中、こうしたシステムを導入することで、情報の整理・共有・活用をデジタル化し、業務全体のスピードと精度を高めることが可能になります。
物件数が多くなるほど管理が煩雑になりがちですが、物件共有システムを使えば誰が見ても同じ情報を同じ場所で確認できるため、社内の連携ミスや情報の食い違いを防ぎ、チーム全体の業務効率が向上します。
概要と役割(物件情報の一元管理・社内外との共有)
物件共有システムの主な役割は、物件情報の一元管理とスムーズな情報共有です。
具体的には、以下のような情報を1つのシステムで管理できます。
- 物件の所在地、間取り、価格、築年数などの基本情報
- 写真や図面、現地案内図などの添付データ
- 販売状況(公開中/交渉中/成約済など)
- 更新履歴や変更ログ
これらの情報を社内の営業担当者がリアルタイムで確認できるだけでなく、提携している他社とも情報を共有できる仕組みを持つシステムもあり、売主・買主・仲介会社をつなぐ情報のハブとして活用されるケースも増えています。
現場に導入することで得られる業務改善効果
物件共有システムを現場に導入することで、以下のような実務的メリットが得られます。
- 情報の探しやすさ・更新しやすさが格段に向上
物件情報を探すたびに別のファイルを開いたり、古い図面を印刷し直す必要がなくなります。 - 共有漏れ・伝達ミスの防止
最新の物件情報が常に反映されているため、社内や協力会社とのやりとりもスムーズ。 - 紹介スピードが早まり、チャンスを逃さない
顧客からの問い合わせに対し、すぐに最新物件を提案できる体制が整います。 - 新人教育にも活用可能
過去の成約履歴や登録済み物件をもとに、物件知識や相場観を身につけやすくなります。
このように、物件共有システムは「情報をまとめて見せる」だけでなく、業務の流れそのものをスムーズに変える武器となるのです。
物件共有システム選びでよくある失敗例
物件共有システムは業務効率を大きく改善できる便利なツールですが、選び方を間違えると、逆に業務の足かせになることもあります。
特に中小の不動産会社では、現場の運用にマッチしていないツールを導入してしまい、「せっかく導入したのに使われない」「むしろ手間が増えた」といった失敗も少なくありません。
ここでは、よくある失敗例を4つ取り上げ、導入前に気をつけるべきポイントを解説します。
高機能すぎて使いこなせない
「機能が豊富な方が安心」と思って多機能なシステムを選んでも、実際には使わない機能が多すぎて混乱の原因になることがあります。
とくに中小企業や少人数のチームでは、必要最小限の機能で十分に業務を回せる場合が多く、高機能=高性能とは限らないのが実情です。
操作画面が複雑で覚えることが多いと、現場では使われず、結局は旧来の方法に戻ってしまうケースも。「現場で本当に使う機能は何か」を明確にすることが大切です。
操作が難しく、現場に定着しない
どんなに便利なシステムでも、現場で使いこなせなければ意味がありません。
とくに営業スタッフや物件担当者は、IT操作に不慣れなケースも多いため、直感的に使えるUI(操作画面)であるかどうかが定着のカギになります。
入力が複雑だったり、物件登録に手間がかかると、「結局エクセルで管理した方が早い」と感じられてしまい、システムが形骸化する恐れがあります。
導入前には実際の画面を見て、現場の声を聞きながら選定することが大切です。
情報共有のフローと合っていない
物件情報の登録や共有方法が、自社の業務フローと合っていないシステムを選ぶと、逆に混乱を招く原因となります。
たとえば、情報の更新や公開範囲の設定が複雑だったり、社外との共有機能が弱い場合、社内外の連携に手間がかかり、かえって非効率になることもあります。
また、「他社と共有したいが、全情報が開示されてしまう」といった仕様も注意が必要です。自社の業務フローを理解し、それにフィットするシステムを選ぶことが成功の鍵となります。
コストが見合わない
初期費用や月額料金が高額で、導入後に「費用対効果が合わない」と感じてしまうケースも珍しくありません。
とくに中小企業にとって、IT投資の判断は慎重になりがちです。必要な機能だけに絞って、無理のない価格帯で運用できるかを事前にしっかり確認することが重要です。
また、導入後に追加費用が発生するケースもあるため、料金体系が明瞭かどうかもチェックしておきましょう。
物件共有システムを選ぶ際のチェックポイント(5選)
物件共有システムを導入する際は、ただ「有名だから」「高機能だから」という理由だけで選ぶのではなく、現場の業務フローや自社の規模感に合ったシステムを選定することが重要です。
ここでは、導入後に「失敗しない」ために押さえておきたい5つのチェックポイントをご紹介します。
現場が使いこなせる操作性・UI
どれだけ機能が充実していても、現場のスタッフが使いこなせなければ意味がありません。
物件の登録・検索・更新が直感的に行えるか、必要な情報にすぐアクセスできるかといった操作性やUI(ユーザーインターフェース)のわかりやすさは、選定において最も重視すべきポイントの一つです。
特にITに不慣れなスタッフが多い企業では、「誰でも迷わず操作できる」ことが、システム定着のカギになります。
導入前にデモ画面やトライアルを試してみるのがおすすめです。
Googleマップ連携や地図での物件管理機能
物件情報を文字だけでなく地図上で視覚的に管理できる機能は、営業活動の効率化に直結します。
Googleマップなどと連携して、物件の所在地・周辺環境・販売状況などを一目で確認できる機能があれば、物件提案の質もスピードも大きく向上します。
さらに、エリア別の成約傾向や物件密集度なども把握しやすくなるため、仕入戦略や価格設定にも活用できます。
営業現場の「感覚」を、地図で「見える化」することで、社内共有や教育にも役立ちます。
他社との情報共有・成約履歴の参照が可能か
自社内での共有だけでなく、他社との連携を前提とした業務スタイルが一般的な不動産業界においては、他社とスムーズに物件情報を共有できる機能も非常に重要です。
例えば、「信頼できる他社とだけ物件を共有したい」「売主情報を隠して物件を紹介したい」といった柔軟な共有設定が可能なシステムであれば、現場のニーズに合いやすくなります。
また、過去の成約履歴を検索・参照できる仕組みがあると、価格査定や顧客提案の信頼性も高まり、営業に説得力が生まれます。
SNSや自社サイトとの連携機能
近年では、物件情報をInstagramやX(旧Twitter)などのSNS、自社ホームページと連動させて発信する動きが活発化しています。
物件共有システムが投稿機能と連携していれば、登録と同時に情報発信まで完結し、集客効率が格段にアップします。
例えば、物件情報を登録すれば自動でSNSやポータルに投稿される仕組みがあれば、営業担当の手間を減らしつつ、情報の露出を最大化できます。
DX化と集客力強化の両立を図るなら、SNS・Web連携機能は必須です。
コストパフォーマンス(料金・導入のしやすさ)
中小不動産会社にとって、導入コストや月額料金は大きな判断材料になります。
初期費用やランニングコストが高すぎると、長期運用が難しくなるだけでなく、現場の導入意欲も下がってしまいます。
一方で、「安いから」と価格だけで選ぶのも危険です。必要な機能が不足していると、結果的に手作業が増えたり、別のツールを併用することになりかねません。
理想は、自社の業務に必要な機能が揃っており、適正な価格帯で使えるシステムを見極めることです。導入前に無料トライアルやサポート体制も確認し、安心して始められるかどうかも含めて検討しましょう。
中小不動産会社におすすめの選択肢:「PPZE(ププゼ)」とは?
物件共有システムを導入する際、「機能が多すぎて使いこなせない」「結局エクセルに戻ってしまった」という声も少なくありません。
そんな中で注目されているのが、中小不動産会社の現場ニーズに特化して開発された物件共有・管理ツール、「PPZE(ププゼ)」です。
PPZEは、「誰でも使える・すぐに使える・使い続けたくなる」をコンセプトに設計されており、導入のしやすさと現場活用のしやすさを両立しています。
関連記事:小規模不動産会社が物件管理システムで大幅に業務改善した話
PPZEのコンセプトと特徴(地図連携・簡単操作・SNS連携)
PPZEの最大の特徴は、物件情報をGoogleマップ上で視覚的に管理・共有できることです。
従来の「文字と表」だけの情報ではつかみにくかったエリアの相場感や物件の分布状況を直感的に把握できるため、仕入れ判断や販売戦略の立案に役立ちます。
また、物件登録・更新作業がとにかく簡単。直感的な画面設計で、誰でも迷わず操作できるのもPPZEならでは。さらに、物件ごとに投稿機能がついているため、その物件に対して議論をやり取りすることができます。
ITが苦手な現場にも優しいシンプルな設計
PPZEは、「現場の人間が“気軽に使える”こと」を最優先に開発されたシステムです。
「複雑な設定は不要」「文字が大きく見やすい」「スマホやタブレットでも操作しやすい」など、現場スタッフの使い勝手を徹底的に追求しています。
導入後すぐに現場で使い始められるため、ITスキルに不安のある企業でも安心して導入が可能です。実際に、ITに詳しくない事務スタッフや新人営業が、初日から違和感なく活用できたという声も多く聞かれます。
成約履歴や社内教育活用も想定した仕組み
PPZEには、単なる物件の管理・共有にとどまらず、過去の成約データや販売履歴を蓄積・可視化する仕組みも備わっています。
この情報は、価格査定や仕入れ時の判断材料として活用できるだけでなく、新入社員や若手営業マンの教育にも有効です。たとえば、「この物件はこの価格帯で成約した」「こういった提案で売れた」といったリアルなデータを見せることで、経験に依存しない育成体制の構築が可能になります。
SNS・マップ・社内管理が一体化した「現場主義ツール」
PPZEは、物件情報の入力・社内共有・他社共有・SNS発信・地図表示・成約記録の保存といった機能を、ひとつのシステムで完結できる「現場主義のオールインワンツール」です。
「複数のツールを使い分ける必要がない」「担当者ごとの業務が分断されない」といった点も、少人数体制の不動産会社にとっては大きなメリットです。
これまでExcelや紙・口頭で行っていた非効率な情報管理を、PPZEが自然なかたちでデジタル化し、業務全体を効率化する足場となってくれます。
現場に根づく仕組みこそ、選ぶべき「物件共有システム」
物件共有システムは、不動産会社にとって「情報の見える化」や「業務の効率化」を実現する強力なツールです。
しかし、どんなに高機能でも、現場で使われなければ意味がありません。
だからこそ重要なのは、“自社の規模や業務フローに本当に合ったシステム”を選ぶこと。
誰が使っても迷わず操作できる、社内外の連携を妨げない、導入しやすい価格帯である。こうした基本を押さえたうえで、DXへの第一歩を踏み出すことが、企業の成長につながります。
その点で「PPZE(ププゼ)」は、情報共有とDXの両立を図りたい中小不動産会社にとって非常に有力な選択肢です。
地図連携・SNS発信・成約履歴管理など、現場の“あったらいいな”を形にした設計で、チーム全体の生産性を底上げします。
まずは、PPZEでどんなことができるのか、公式サイトでご確認ください。
→ https://ppze.jp/